火事注意。マネするときは自己責任で!
RaspberryPiを複数台起動するときや、モーターやほかの基盤にも別電源が必要だったり、そんなことありますよね。
そんな時、パソコンからまとめて電源取れないかな?と考えてしまいますよね。
そんなわけで、今回はそれを試してみました。
ジャンクPCで部品がそろいます
まず、電源を取り出しますが、今回はパソコンの前面パネルのUSBもとりだして使用しました。

フロントパネルのUSBは、マザーボードに配線されています。
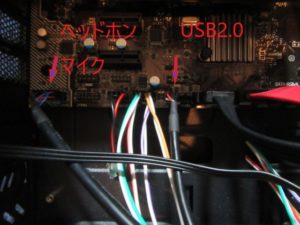
USB3.0は別にマザーボードの電源コネクタの横。基盤右側についていることが多いと思います。

ただ、今回は電源を取るだけなので、USB3.0を壊すのはもったいないです。
もっと古いパソコンから部品をとったほうがいいと思います。
フロントUSB流用で、電源を取ると、
結果としてはこのような感じになります。

ヘッドホン、マイクは不要なので、線を切っています。
どの線をどうつなぐか
パソコンのスイッチ線
パソコンはスイッチを入れてはじめて起動します。
ですのでPC電源をそのままコンセントでつないでも電気は流れません。
スイッチを無効にします。
それには電源についている一番大きなコネクタを見ます。

緑色の線がありますね。これがスイッチの線です。
私の持っている電源では全て緑色でした。
そして電源では他に緑色の線はありませんでしたので、
すぐに発見できると思います。
これを黒のマイナス(GND)と直結すればスイッチが無効になります。
どのGNDと配線しても同じですよ。

電源各線のボルト数
もしかしたらメーカーによって違うことがあるかもしれませんので、参考程度に思ってくださいね。
赤 5V(ラズパイは5Vで起動します)
オレンジ 3.3V
黄色 12V(カー用品や、ラジコンバッテリーの安定充電)
黒 GND
緑 スイッチ
紫は5VSBで常時電源のようなものとの情報がありましたが、今回は使用しないので確認はしていません。
USB側の配線
USBには4本の線があり、両端2本が電源。
真ん中2本がデーター線です。
実際の基盤で確認すると
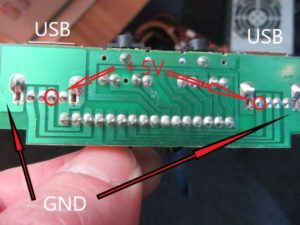
USBが端に2つあります。そして基盤の面積の大きい部分がマイナスです。
ですから、端から数えて真ん中2つ飛ばしたところが、USBの+5Vになります。
後は、基盤を裏返して、線の色を確認して配線すればよいのです。
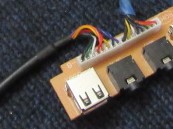
この時に確認するのはマザーボードのUSBに刺さっていたほうの線ですよ。
※ 見分け方
ヘッドホン、マイク端子
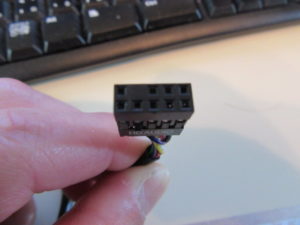
USB3.0端子

USB2.0~USB1.0
1列型と、2列型があります。


配線について
絶縁
不要になって切った線はショートしないように何かでカバーします。
絶縁テープ

熱収縮チューブ
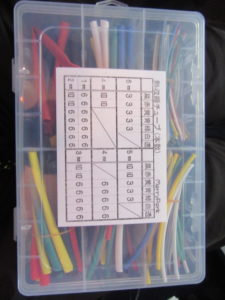
配線する前に片側の線に通しておいてはんだ付け後にカバーします。
熱でチューブが縮んでフィトします。ヒートガンを使うのが正しいようですが、私はライターで軽くあぶっています。
はんだ付けが苦手
電光ペンチが必要になりますが、キボシ端子を使うのも手です。
線を挟んでつぶします。

こんなものもあります。
普通のプライヤーがあればできます。

配線する線を穴に入れて

プライヤーでがっちりしめればもう絶縁までできちゃいます。
完成状態

5V電源が取れています。
今回はほかの電圧の線もそのままとっておきました。
後々、モーターなどで、ロボでも作りたくなったら別電源が欲しくなるかもしれません。
これでアダプターだらけから解放されます(笑)
※ これだけだと少し電力不足のようです。
+GPIO給電を試してみました。こちらの記事です。
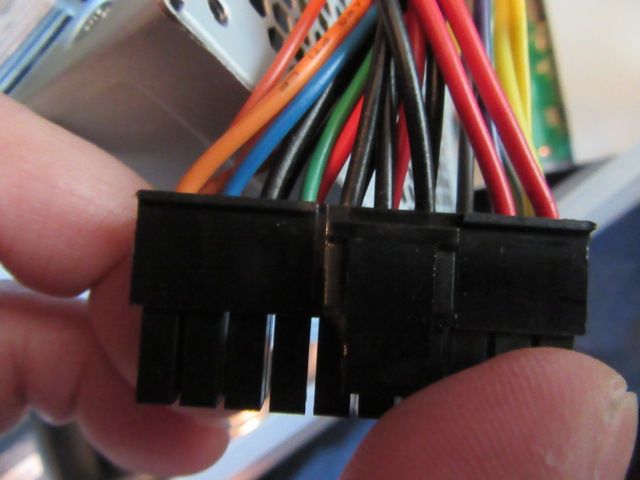
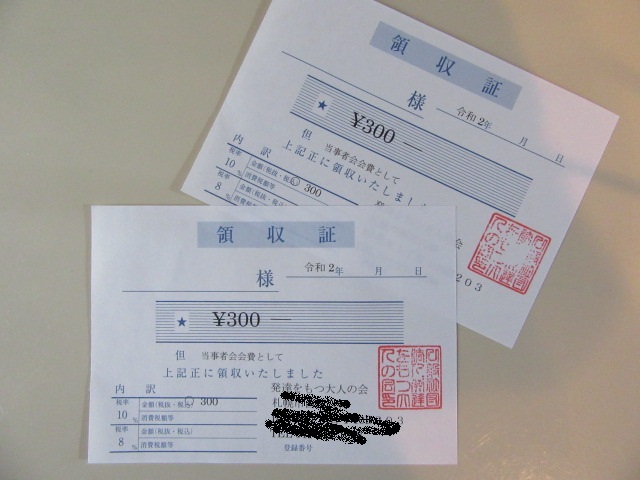

コメント